子育てで「子どものために」と思うほど苦しくなる時があります。
そんな時に思い出してほしいのが、『自分軸』の考え方です。
「子どものためにできることをしたい」「少しでも力になりたい」
そう願うのは、親として自然な気持ちです。
でも、気がつくと
子どもの表情や反応に心が揺れて、自分の気持ちが揺れ動いてしまうことはありませんか?
「今日は機嫌がいいみたい、よかった」
「またイライラしてる…私の対応が悪かった?」
「学校はどうするのかな。行ってくれるといいけど。はぁ…(ため息)」
そんなふうに、子どもの状態で自分の感情が決まってしまうとき、私たちは知らず知らずのうちに『他人軸』で生きてしまっています。
「この子のために」という思いは尊いけれど、
度が過ぎると自分を責めたり、心がすり減ってしまうこともあるのです。
子育てにおける「自分軸」と「他人軸」の違いとは?

『自分軸』とは、自分の感じ方・考え方・価値観を大切にして行動すること。
つまり、「私はこう思う」「私はこう感じた」と、自分の内側の声を大切にして生きることです。
『他人軸』とは、相手の反応や評価を基準に行動すること。
「どう思われるかな」「嫌われないようにしなきゃ」と、相手を中心に考えてしまう状態です。
例えば、
-
子どもが不機嫌だと、自分まで落ち込んだり不安になる
-
周囲の目を気にして、自分の判断が揺らいでしまう
-
本当は「これがいいな…」と思っているのに相手に合わせて「それがいいと思った!」と合わせてしまう
これらは『他人軸』のサインかもしれません。
子どもとの関係でもそうですが、配偶者・親族・友人など全ての人間関係で役にたつ考え方です。
思春期の子に「うるさい!ほっといて!」と言われた時
思春期は子ども自身も感情がコントロールできず苦しい時期です。
とはいえ、暴言には落ち込みますよね。
他人軸で受け取ると…
-
「私が悪い母親なのかな」
-
「なんなの⁈ 親に向かって‼︎」
-
「どうしてこんなこと言われるんだろう…」
と、相手の言葉や態度に心が揺さぶられ、罪悪感や悲しみ、怒りでいっぱいになってしまいます。
自分軸で受け取ると…
-
「この子は今、心がいっぱいいっぱいなんだな」
→私は思春期ではないのでそんな状態ではないけどね! -
「その言葉は悲しいけど、私はちゃんとやれることをやっている」
→衣食住整えてます! -
「私はこの子を大切に思っている。それは変わらない」
→母の愛はこんなことでは変わりません
と、自分の感情を認めながらも、相手の感情と自分の感情を切り分けて考えることができます。
不登校の子が部屋にこもってしまい会話がない時
お母さんとしては心配な状況ですね。
他人軸で受け取ると…
-
子どもの態度に一喜一憂してしまう
-
「なんとか話してほしい」と焦る
-
「自分がもっと頑張れば、この子も変わるかも」と思い込む
-
周りの親や先生の言葉に振り回される
この状態が続くと焦りや不安が募り、どんどんお母さんの心が疲れてしまいます。
自分軸で受け取ると…
-
「この子を信じて見守ろう」
→大丈夫! -
「私は毎日声をかけている、それで十分」
→無理やり学校行かせることはできないもんね -
「この子のペースでいい。焦らなくてもいい」
→子どもの人生は子どものもの
というように、自分にできることと子どもの課題を分けて考えられるようになります。
お母さんが穏やかでいることが、そのまま子どもの安心感になります。
今すぐ会話がなくても、お母さんが穏やかに過ごしている姿は、子どもにとって信頼できる環境そのものなんです。
他人軸で生きると心が疲れていく理由

他人軸で生きていると、『相手の気分』に合わせて行動することになります。
特に家族の中では関係が近いがゆえに、『相手の気分』を感じやすくなります。
子どもが元気なら安心できる。
子どもが落ち込んでいると、自分まで不安になる。
自分の心が相手の天気に支配されてしまいますね。
私も子育てをしてきました。
ある程度は子どもの心の状態に揺れ動くのは仕方ないかな…と思っています。大切に守り育ててきた子ですもんね。
本来、子どもの機嫌も元気もやる気も、すべて子どものもの。
そして、お母さんの機嫌もやる気も、お母さん自身のものなんです。
お母さんが「なんとかしなきゃ」と抱え込むものではありませんし、なんとかできるものではありません。
子どもの人生の舵は子ども自身にしか握れません。
お母さんは横で見守りながら、自分のペースで穏やかに過ごしていいのです。
自分軸を取り戻す3つのステップ
不登校や思春期の子育てでは、自分軸を保つことがとても大切です。
子どもの様子を見て心がざわつく時にはこう考えてみましょう。
ステップ1:自分の感情に気づく
まずは、「今の私はどう感じている?」と立ち止まってみましょう。
子どもの様子ばかり気にしていると、自分の感情が見えなくなります。
「あれなんだか今日はすごくざわつく」「疲れちゃったな」「今日は静かに過ごしたい」そんな気づきで十分です。
その感情に気がついた時には自分をいたわってあげてくださいね。
ステップ2:「これは誰の課題?」と問いかける
子どもが学校に行かない、元気がない、イライラしている。
つい一緒に悩み、解決したくなりますが、「それは誰の課題だろう?」と自分に聞いてみましょう。
アドラー心理学でいう『課題の分離』の考え方です。
相手の課題に踏み込みすぎないことで、心の境界線を守れます。
ステップ3:自分のペースと選択を大切にする
お母さんが穏やかでいることは、子どもにとって安心の土台になります。
「これ、私が悩んでいても変わらないよね」
「今日は少し散歩してこよう」「温かいお茶をゆっくり飲もう」
そんな小さな自分時間が、心の軸を整えるエネルギーになります。
日々、小さな自分時間をつくってください。
その積み重ねは自分の心を整える大きなエネルギーになります。
自分軸を貫ぬかなくていい

「貫く」よりも「戻る」
「自分軸を貫く」と聞くと、
いつもブレずに堂々としていなければならないような気がしてしまいます。
でも本当は、ブレても大丈夫なんです。
人は人間関係の中で生きているので、
他人の目や言葉に影響を受けるのはごく自然なこと。
大切なのは「ブレないこと」ではなく、
ブレたあとに自分に戻ってこられることです。
たとえば、
「あの人はこう言ってたけど、やっぱり私が間違ってるのかな…」と感じたときに、
「でも私はこう感じたな」「私にとって何が大事だったっけ?」と少しずつ自分に戻る。
これが現実的で優しい『自分軸』です。
「外に出す自分」と「内にいる自分」を分けていい
他人と関わる場面では、自分のすべてを出す必要はありません。
-
外に見せる『社会的な自分』
-
内に持っている『本音の自分』
この2つがあるのは自然なことで、どちらも大切な自分です。
たとえば職場やママ友との雑談の場面で、「自分の意見を言うと浮きそうだな」と感じたら、無理に貫かなくても大丈夫。
場の空気に合わせる選択をしてもいい。
私がよく使う作戦は『否定も同調もしない』です。「へぇー。そう考えるんですねー」と微笑みます。
ただし、自分の本音を心の中で否定しないことが大切です。
「あの人はそう考えてるんだなぁ。今は言わなかったけど私はこう思ってる」と、自分の中で認める。
それだけで、自分軸はちゃんと生き続けています。
自分軸は孤立ではなく、柔らかく立つイメージ
自分軸というと、他人に左右されず強く立つように感じがちですが、
本来は自分も相手も大切にする『しなやかさ』です。
たとえば…
思春期の子どもがイライラしている時に、お母さんが自分軸を保つというのは、
「子どもの機嫌に合わせるな」という意味ではなくて、
「自分の心まで一緒に乱さないようにする」ということです。
同じように、他者の前で意見を曲げる場面があっても、
「その時の自分は周りとの調和を大切にしたんだな」と受け止めると、
自分を責めずにいられます。
おわりに
誰かのために頑張ることは素晴らしいこと。
でも、それ以上に大切なのは、自分の心を守ることです。
苦しい時には『 自分軸 』を思い出して!
自分を大切にできる人が、本当の意味で人を支えることができるから。
子育て中のお母さんが自分軸を整えることで、子どもとの関係も変わります。
今日もあなたが、自分らしいペースで心穏やかに過ごせますように。





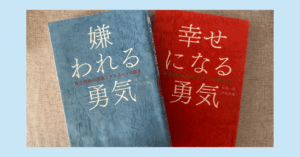
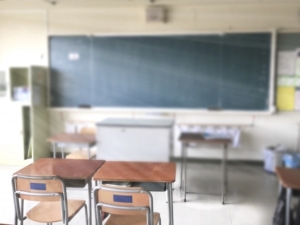


コメント