最近、朝なかなか起きられないし、体がだるくて動けないみたい…。
でも熱もないし、夜はいつまでもyoutube見てるし…。朝起きれなくて当然‼︎
起立性調節障害や自律神経の乱れは、あきらかな症状が見えません。元気そうに過ごしている時間もあるだけに親としてもどう関わったらいいのか迷いますね。見方のよっては「怠けている…?」と思えてしまったり。
今回は、おうちでできる小さなケア方法をまとめました。子どもに合いそうな事やできそうなことから一歩ずつ始めてみてくださいね。
自律神経が乱れることは大人にもあることですが、今回は「不登校の子に対して」という場合を想定しています。
自律神経を整える生活習慣
①朝はまず「太陽の光」を浴びる

自律神経は体内時計と深く関係しています。
朝起きたらカーテンを開けましょう。太陽の光を浴びることで体内時計がリセットされ、自律神経の切り替えがスムーズになります。
人間の体は、地球の自転による24時間周期に合わせ体内環境を変化させる機能を持っています。体温やホルモン分泌など、からだの基本的な機能は約24時間周期のリズムで働いています。
例えば、メラトニンというホルモンは体内時計と深く関わり、日中は覚醒、夜になると自然な眠りへ導くために分泌されます。
この体内時計をコントロールしているのは、脳の視床下部にある視交叉上核(しこうさじょうかく)という部分であり光の情報を受け取り、睡眠やホルモン分泌など体のリズムを整えます。
ですので、朝に太陽の光を浴びることが身体のリズムを整えるのに非常に役立つのです。
「早起きしてウォーキング!」など意識高く持たなくても大丈夫です。子どもが起きてくるかわからないけどリビングには太陽の光を取り込む習慣をつけておく…など、できそうなことから小さく始めてみてください。
起立性調節障害の特徴
気圧の変化と起立性調節障害には深い関係があります。
気圧が低いと血管が広がりやすくなり、血のめぐりがゆるやかになります。すると、立ち上がったときに脳に十分な血が届かず、めまいや立ちくらみが起こりやすくなるのです。
どんなときに注意が必要?
・台風が近づいているとき
・雨の日
・急に暑くなった日や寒くなった日
こうした日は特に自律神経ががんばって体を調整しようとするため、疲れやすくなったり、症状が強くなったりします。
こんな日があることを知っておくだけで「今日は無理しない日」と、いたわることができそうですね。
②副交感神経を優位に
上記の記事で紹介している通り、交感神経は活動、副交感神経は休息という働きをしています。
そもそも自律神経が乱れていたり、起立性調節障害などでつらいときは、交感神経ががんばりすぎている状態です。
お布団から出てこず眠っているように見えても、心と身体がずっと緊張し、うまく休めていなかったりすることが多いのです。
だからこそ、副交感神経を優位にする=リラックスする時間を増やすこと がとても重要になります。
こんなことを意識してみよう
・お風呂にゆっくり入れている?
・好きな音楽を聴いたり関心のあることができている?
・ゆっくりと呼吸ができている?
・ペットをなでたりするなどリラックスする時間は作れている?
・自分の気持ちを吐き出せている?(聞く人は否定せず受け止めてあげましょう)
・学校を休むことに罪悪感は感じていない?(ゆっくり休んでいいことを伝えてあげましょう)
上記はほんの一例です。
子ども自身が好きな事や好きな物に囲まれ、心と身体が緊張しない環境に身を置くことが大切です。
大切なのは、親が考えるリラックスできる環境ではなく、子どもが心から「休めている」と感じることです。
③バランスの良い食事と水分補給

朝ごはんが食べられない子も多いのですが、少しでも口にできるもの(ゼリーやスープなど)をとるだけでも違います。
脱水はめまいやふらつきの原因になるので、水分はこまめにとりましょう。
起立性調節障害の場合
起立性調節障害の症状が出る要因の一つが脳の血流の低下です。
起床時や起立時に顕著になります。脳の血流改善のためには身体を循環する血液量の増加が必要であり、水分摂取は血液量を増加させる有効かつ簡便な方法です。
④スマホやゲームへの考え方
夜遅くまでスマホやゲームをしていると、睡眠の質が下がり、自律神経にも影響します。「使いすぎないように」と言うのではなく、「一緒に使い方を考えようか」と寄り添う姿勢が大切です。
しかし、子どもの心の状態によってはスマホやゲームを手放さない時期があるかもしれません。そのような状態の時に無理やり取り上げるのは余計に心の状態が悪化していくと考えられます。
ゲームなどで時間を潰していないと心が壊れてしまいそうになるのかもしれません。学校のことや将来のことなどを考えないで済む時間なのかもしれません。
まずは「そんな心の状態なのもしれない」と考えてみてもいいかもしれません。
親にできること

⑤「何もしない」も大事なケア
子どもの休みが続いてくると、つい「早く元気になってほしい」と思って色々やってあげたくなりますよね。
でも子どもにとって一番必要なのは、安心して休める環境です。
あれこれ指示されたり、元気になることを急かされたりすると、子どもは「早く治らなきゃ」とプレッシャーを感じてしまったり「うるさい!」と反発したくなるかもしれませんね。
そのストレスは、自律神経の回復を遅らせてしまいます。
いろいろ言ってしまいそうになる気持ちはグッと堪えて、見守る時間も必要です。見守るというのはただ放っておくわけではありません。
・安心できる環境を整える
・必要な時や子どもが求める時だけ、そっと手を差し伸べる
・体調が良さそうな時には学校や体調のことではなく、何でもない話をしてみる。
このような関わりが、子どもが「自分のペースで回復できる」という安心感につながります。
その安心感こそが、元気を取り戻す力を育てるのです。
⑥子どものペースを尊重する言葉かけ
親は少しでも元気そうな様子が見えると、なんとか解決の糸口を見つけようと学校のことや生活リズムのことなど話したくなってしまうかもしれません。
自分のことに置き換えてみてください。
例えば、熱が出ていたけど解熱剤で下がっている数時間、何をしますか?
何をした方が良いと思いますか?
体調の悪さをわかってくれていない人から急かされるような声掛けをされても不信感しか湧きませんよね。
(今、これを書きながら「まさにこれやってた…」と猛省しています…)
子どものつらさに寄り添いましょう。自律神経の乱れには「お母さんはわかってくれてる。今はゆっくりしていていいんだ」「安心、安心」という思いが大切です。それが子どもの心に定着してやっと少しずつ元気が出てきます。
⑦親自身が整っていることの大切さ
不登校であったり体調不良の子どもを支える日々は、どうしても親に大きな負荷がかかります。
この状態が続くと、親自身の自律神経も乱れやすくなり、疲れやすい・眠れない・気持ちが落ち込みやすい…といった不調につながります。
親が元気でいることは、子どもに安心感を与えるだけではありません。親自身が長く無理なく子どもを支えられる体力と心の余裕を保つことにもつながります。
だからこそ、親が休む時間や自分を労わる時間を持つことはとても重要な自己ケアです。
学校を休んでいても焦らなくて良いことや、自律神経の乱れも良くなることなどを子どもに伝えるだけではなく、親自身がそれを納得して子どもと関わることが大切です。
親自身の納得は子どもに安心感を与えます。それが子どもが「休む」ことの始まりです。
つらさが溜まりきる前にカウンセリングを受けたり、信頼できる方に胸の内を話してみたりして自分のことも大切にしてくださいね。
こんな時は受診を考えて

日常生活に支障が出ている時
食欲がなく体重が減っていたり、元気がなく、抑うつ的な様子が続いている場合には受診しましょう。
そもそも健康的に過ごしている状態ではないので、気がつきずらいかもしれませんが、
・調子のいい時間にはこのくらい食べられていたのに最近それもできていない
・ボーッとしている時間が多い
・なんか…ちょっと…
など、調子が悪いのは前提にあるけれど、いつもと違うという感覚がある時にはかかりつけ医や心療内科、精神科など早めの受診をおすすめします。
近くで様子を見ているご家族の「なんか…ちょっと…」という感覚はとても大切です。「はっきり説明できないから…」と先延ばしせず受診しましょう。
子どもに無理をさせず、親も無理をせず、専門家と繋がることはとても重要なことです。
おわりに
家庭でできそうなケアを7つご紹介しました。
自律神経の乱れや起立性調節障害で不登校になると、子どもの体調、学校や将来のこと、たくさんの不安・心配を抱えることになります。いろいろなことを上手にこなしていくのはとても難しいです。
子どもの命を守りながら、できることを少しずつ…取り組んでいきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます!


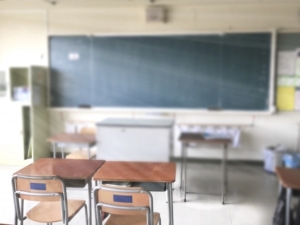
コメント